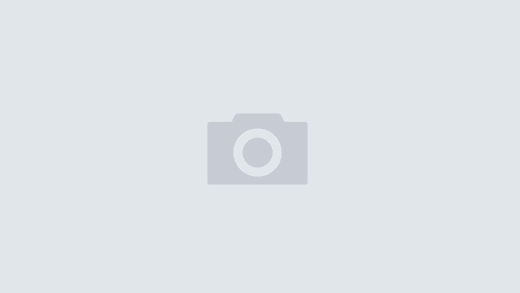西暦2053年4月9日 杉山隆文の場合
<セクション1>
俺の名は杉山隆文。今、依頼主とともに、ひとりの少女を追い詰めたところである。
「わかった。降参。あんたに負けを認めるわよ」
目の前の美少女は、俺とトーヤとスクランブルの3者に囲まれてようやく、勘弁したようだった。
「まさかスタンプまでトーヤの応援にまわるとは」
紺色のワンピースを着た美少女・・・エリザベスが諦めたように、首を振る。
「先に雇われたからな。、、、そもそも、お前が逃げ出さなかったら、こんな思いもしなかったんだ」
俺もワイフォンを下ろしながら、苦虫を潰す。
「で、どうして?同棲先から逃げたんだ?」
「だって、この男。同棲初日に一緒にお風呂に入ろうなんて言い出したのよ?!」
エリザベスの発言に顔を赤らめるトーヤ。
たかがそれだけのことで、と思うだろうか。いや、実は無理もないのだ。
彼らの生きていた時代はもはや恋や家族はレジャーだった。人工授精で生まれる生命が増え、くちづけすらも嫌われた時代。当然、トーヤの希望は犯罪と受け止められても仕方がなく、新時代の認識として、エリザベスが嫌うのは当然だ。
誤解も可愛いというかなんというか。
「まあ、お前らが同棲したのは、2021年のことなんだろう?時代の風潮を考えろ」
俺はやんわり、エリザベスを諭す。
「それなら、この時代の男性はレディにはどう接するのよ。智弘父さんなら、こんな時、美味しいご飯くらい作ってくれたわよ」
「へいへい。美味しいご飯ね。・・・行こうか、トーヤ」
古き良きNAGASAKI。老舗の中華料理店に足を運ぶ俺たち3人。
郷土料理のちゃんぽんを啜りながら、冷え切った体を温める。
「・・・」
ずるずると3人で、海鮮ちゃんぽんをすする。具がたくさんの麺がお腹の中でハーモニーを奏でていく。
「なんかちがーうっ!!」
うるさいなぁ・・・。誰なんだ、この娘に食育を施したバカチンは。
「こんな時は、満漢全席よっ!」
「それもちがうだろ。金は自分で払え。俺は知らん」
「スタンプさまー。そりゃないわー!」
くどいようだが。
俺の名は杉山隆文、またの名を「スタンプ」。しがないNAGASAKIの探偵である。
<セクション2>
翌日。とりあえず、トーヤとエリザベスを手錠で繋ぐことにした。
「ちょっと、なんなのよ。これ」
エリザベスが恨めしそうに自分の右手を見る。
「仕方ないだろう。また、お前が逃げないための苦渋の決断だ」
俺には、別件の仕事が控えていた。
雇用主から与えられた重要案件が2つ。これから、人と会わなければいけない。
「鍵は俺が持っておく。夕方には帰るからおとなしくしてろ」
「待ちなさいよ。トイレやお風呂はどうしたらいいのよ!」
「風呂はあきらめろ。トイレはトーヤと一緒に入ればいいだろ」
『え・・・』トーヤとエリザベスが青ざめた。
「ちょっとちょっと。それ何よ!」「まってください、スタンプさん!」
「同棲していたんだろう?トイレくらいノープロブレムだ」
「変態プレイはやってないっ!」「そうですよ!」
鬱陶しいガキどもだ。
「足は自由に動かしてかまわない。工夫して、2人の共同作業で今日を乗り越えろ」
俺は、事務所を出る。
この行動には理由がある。
これから半日以上。いやでも、トーヤとエリザベスは話さなければいけない。
その時間で、何かが解決するかもしれない、と思ったのだ。
「荒療治ですね。マスター」
スクランブルが足元で呟く。「うまくいくでしょうか?」
「まあ、どっちにしろ、逃げたら、また探せばいい」
つぶやいて、俺は愛車のKATANAのイグニッションキーを回したのだった。
<セクション3>
「あら、まあ。そんなわけだったのね」
メッセンジャーアプリで、少女がつぶやいた。
少女は俺の雇用主。安倍あやの。大富豪マッカトニー家の資産管理責任者。
幼いながらに、優秀な女性で、これでも国内外の複数法人の立ち上げと運営にかかわる重要人物。
今、彼女はイギリスにいる。
「2人ともお前さんの親戚なんだが、、、申し訳ないな」
「そうね。今回は多めに見るわ」
そこで話題が変わった。
「今回の依頼はボディガードよ。あわよくば、依頼主を狙っている黒幕をつきとめてほしいの」
ワイフォンに送られた調査依頼書を見ると、女性4人のアイドルグループの名前が記載してあるようだ。
「ラブ☆マスターズ・・・って、これまた俗な依頼だな」
「今ありがちの国際的な声優アイドルユニットよ。あなたなら楽勝でしょ。近日、ハイブリッドでコンサートが開かれる予定なの」
コンビニのホットコーヒーで体を温めながら、電子タバコで一服する。
ワイフォンのBluetoothイヤホンから、音声が響いた。
「詳しくは現地のマネージャーから、指示を受けて」
「わかった」
<セクション4>
その頃、探偵事務所にて。
「まったくひどい仕打ちだわ。ママに訴えてやる!」
「そうそう、スタンプさんは何を考えているんだ」
エリザベスとトーヤはつぶやく。
「何言ってんのよ。そもそも、あなたが仕組んだんでしょ?」
「ちがう!こんなのは計画してない!2人でお風呂がダメなのに、トイレなんて難易度高いだろう!」
「私が話してるのは性的趣向の話じゃない!」
左手のストレートがトーヤの右頬に入る。
勢いで吹っ飛んだトーヤに絡まって、もんどり打つ2人。
「・・・」「・・・」
しばらくの沈黙。肌にまとわりつくような嫌な時間が流れる。
「ママなら、どんな風にしてこの状況から脱出するかしら?」
ぶつぶつとエリザベスがつぶやく。
「そうだなぁ・・・ひな様ならきっと、日頃から高周波ナイフを持ち歩いているし、、、そもそも、逃げようなんて最初から考えないだろ?」
嬉しそうに話すトーヤに、エリザベスのジト目。
「・・・」
「どうした?」
「・・・あなたがママのことを話すとなんかむかつくのよ!」
「君が話を始めたんじゃないか!」
ごとん。
案の定、絡まった2人が今度は、ソファにもんどり打った。
エリザベスは繁々と右手の手錠を見る。
「これ電子錠ね。多分、20世紀の車のドアに使ってあったのと同じ原理」
「特殊な電磁波で開くってことか?」
エリザベスが懐を探る。
「覚えがあるわ。さんざん、私の部屋の鍵をこれでママが閉めてたもの」
「あ」
「・・・何よ?」
「だったら、この手錠、ひな様なら外せるんじゃないか?」
2人の顔が、これ以上もない悪魔の輝きを見せた。
<セクション5>
打ち合わせを終えて、俺はその日の夕方、探偵事務所に帰ってきた。
「・・・」
事務所は無人。エリザベスとトーヤは まんまと手錠をつけたまま逃げ出したらしい。
「まったく、あの悪ガキどもめ」
ワイフォンを起動して、手錠のGPS情報を追跡する。
すぐに現在位置が表示された。
「今、どうやら、新幹線に乗ったようですね。行き先は、OMURAってところでしょうか」
と話すスクランブル。
「・・・ああ、そういうことか」
彼らの意図が透かしてみれた。
にやりと笑みが溢れる俺。これは、予想以上の収穫になるかもしれない。
「マスター。追いましょう」とスクランブル。
「いや、現状でOKだ」
「・・・あなたの企みは、さしものHANAでも解析できません」
褒め言葉ととっておくよ。
と俺は言葉を飲み込み、仮眠をとるためソファに身を沈めたのだった。
<セクション6>
「スタンプさんは、2つの点を見落としている」
トーヤとエリザベスは、NEW OMURA ステーションに降り立った。
新幹線から降りて、一面に広がる桜並木。
「鍵を外せるひな様がこの時代にいること。そして、時代は違えど、僕らがこの街の地理に詳しいこと」
こくり、とうなづくエリザベス。
「つまり、彼女の居場所を僕たち2人は知っているんだ」
知らないはずがない。なぜなら、そこは、レディ・ヒナの祖母トモエが暮らしていた家。
16歳になって、実際にトモエとエリザベスが過ごした懐かしい家だ。
「・・・あのさ。トーヤ」
エリザベスがボソリとつぶやく。「やっぱり私たち、あのままスタンプを待ってた方がよかったんじゃない?」
「何、いまさら怖気付いているんだよ、エリザベス!」
「だって、、、いや、いい」
言葉をにごすエリザベス。
トモエの住んでいた家は管理が行き届いて、人が住んでいた。
記憶と記録が正しければ、間違いなく、ここにひながいる。
意気揚々と玄関のインターフォンを鳴らす。
玄関に現れたのは、白髪頭の初老の男性だった。
体格はほどほど。それでも無駄な脂肪は一つもない帽子姿のダンディなおじいさん。
「どちらさまですか?」
男性が流暢な日本語で、2人を見る。
「・・・え?」
トーヤとエリザベスの表情が硬直する。
てっきり、お手伝いさんか、ひな本人が出ると思っていたからだ。
「えっと、、、、誰?」
「・・・待ってよ、トーヤ。この人は・・・!」
「なんだよ、エリザベス。さっきから、やけに君らしくないぞ」
「だって・・・。まさかって思ってたけど」
小声で2人はやりとりする。
その様子に男性が穏やかな笑顔をむける。
「仲のいいお二人ですね。美味しいダージリンはいかがですか?」
招かれた2LDLKの家の中は、すっきりと片付いていた。
部屋の壁には、いくつかの油彩画が飾られ、優しいハーブの香りがほんのりと薫っている。
リビングの大きな円卓に、トーヤとエリザベスは座る。
「この絵、見覚えあるわ」
エリザベスの記憶にあるということは、この家には間違いなくひなが住んでいるということだ。
「さすがお目が高い。YOKO OKANOの油彩画。家内が大事にしているコレクションのひとつです」
おじいさんが説明しながら、壁の絵を眺める。
「今、お恥ずかしながら、仮眠から起こしてきますので」
差し出された紅茶を受け取るトーヤとエリザベス。
「あら?エリザベスじゃない。あとトーヤくんも。本当に何年ぶりかしら」
そして、声が聞こえて、起きてきたひとりの女性。
44歳のひながそこにいた。
<セクション7>
「あいかわらずねえ。スタンプならやりそうな話だわ」
話を聞いて、ゲラゲラと屈託なく笑う、ひな。
手元の電子端末であっさり手錠の鍵を外し、トーヤとエリザベスは肩を撫で下ろす。
「どうやって、自動改札口を通ったのよ?まさか手錠つけたまま?」
「有人改札を通りました」
「じゃあ、トイレは?」
「まあ、女子トイレは個室ですから。人気のない時に。目隠しはされましたけど」
「音はしっかりきこえるてるじゃない。はっずかしーっ!」
「ママっ!!笑い事じゃないわよっ!どれだけ恥ずかしかったことかっ!」
顔を真っ赤にして、エリザベスが叫ぶ。
「まあ、それくらいのトラブル、人生にはつきものよ。2人は今、同棲してるんでしょ?」
「・・・同棲初日に別れたわよ。こいつはただのストーカー!」
「どういうことだい?私には話がぜんぜん見えないんだが」
それまで黙っていたおじいさんが、口をひらいた。
「ああ、二人には紹介がまだだったわね。この人、私の旦那様」
あっけらかんと、おじいさんの肩を叩く。
「え?」
「・・・やっぱり」
トーヤとエリザベスが独白する。
「これはどういうことだい、リズ?」
「あなたは、恋人の父親も知らずに同棲してたの? このおじいさんはマーク・マッカートニー。
血のつながった正真正銘の私の父親よ」
<セクション8>
俺は探偵事務所で、パソコン端末を眺める。
コンサートの警備は順調だ。相変わらず、脅迫は続いているが、身辺に変化はない。
ただ、技術的に問題が残っているがそこは、ユグドラシルのひろみと連絡をとって、力を借りることにしよう。
仕事の段取りをつけたとき、スクランブルの視線に気づいた。
「・・・ところでいいんですか?あの2人は?」
スクランブルが口を挟む。
電子タバコを一服ついて、俺はコーヒーをひとくち飲む。
「いいんじゃないか?放置プレイで」
「さてはマスター、トーヤとマークさんを会わせるつもりでしたね?」
心を読んだようにスクランブルが俺を見る。
まあ、多少計算外のこともあったが、この時間軸のひな博士が結婚していた事実に気がつけば、この結末は容易に想像できた。それに知らない仲ではない。俺は実際、大浦天主堂でのマークとひなの結婚式に同席したのだ。
「さて。ここからだぜ、お二人さん。
元恋人のストーカーが、父親からお許しをもらうのは並大抵のことじゃないぜ?」
「まったく。あなたってひとは『こんなときも』変わりませんね」
スクランブルが呆れたようにため息をつく。
「ああ、当然だ。こんなときだから変えちゃいけないんだよ」
笑顔で答えながら、俺はコーヒーカップを、ゴミ箱めがけて放り投げたのだった。