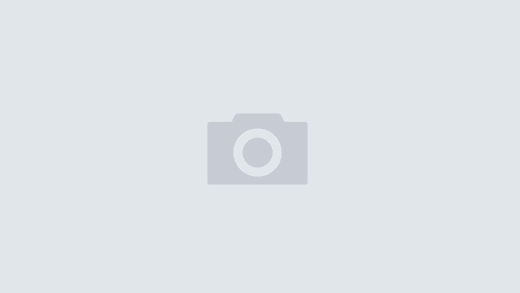西暦2075年4月21日 山本ひろみの場合
<セクション1>
私は、山本ひろみ。
2075年現在、イギリスにある研究所「チーム・ヴァルハラ」の開発チームに所属している。
担当は有機コンピューターのインターフェース管理。現在は、多時代に存在するHANAの有機端末・コードネーム=スクランブルとの交信とそのサポートを担っている。
「副主任、スクランブルからの定時連絡が入っています」
研究所にくるなりの、朝一番の報告はもはや日課だ。
「わかったわ。こっちの端末に回して」
「はい」
画面のチャットに答えると、音声画面が切り替わる。
「やあ、ひろみ。おはよう」
「おはよう。ジョージ。ご気分はいかが?」
「おかげさまで、いつでも最高さ」
私が話すのは、HANAの中に存在するスクランブルの魂。その基礎は人の魂をベースに構成した、私の恋人ジョージの意識体。そう、事故で肉体を失った彼は、今、人工知能の生態パターンとして生きている。
「定点の報告を送ってくれる?」
履歴が一気に送信される。
スクランブルは、いくつかの時代を同時に生きている。その莫大な情報量は言語での限界をこえているので、直接生データのままで管理しているのだ。
目を通していた私は、その情報に気がついた。
「・・・ん?なにこれ、警告が出ているじゃない」
朝の甘い時間、一気に緊張が走った。
報告が示す時間軸は2053年4月。
このままだと、チーフ、、、ヒナ=マッカートニーの命が危ない。
<セクション2>
私が話しているのは、時間事故が発生した、、、つまり、時間の回復力を超えて過去が塗り替えられたという事だ。このまま放っておくと、現在という時間は一気に崩壊してしまう。
「この時代の時間管理局の担当は誰?」
時間管理局・・・いわば、時代が変わらないための監視機構。時間の警察といえば、わかりやすいだろうか。
「過去のチーフの身柄は厳重に警備されていたはずだけど」
これはヴァルハラの所長でもある、ひな自身に相談していいものか悩んだが、彼女以外にこの複雑な時間軸をもとに戻せる人を思いつかない。
私は直接、一報を入れた。こんな状況だけに、アポはすんなり通った。
昼過ぎ、チーフ室を訪ねると、仮眠から目を覚ましたところだった。
耳にヘッドフォン。何かの音楽を聴いていたようだ。
報告はすでに済ませてある。
今の時点、彼女は2053年と2075年を同時に生きている。
「確かに記憶もあやふやだけど、そもそもトーヤくんとエリザベスが会いに来たことがきっかけだったような・・・。ああ、そうだ。それで大変なことになったなぁ」
「つまり、やはりチーフの旦那さんとトーヤくんが出会ったことが原因なんですね」
「ええ、マークがとんでもないこといいだしたのよ。たしか」
懐かしいように話す。
「どうしますか?この件を解決するには、トーヤくんを見捨てるしかなくなりますけど」
物騒だけど、それしかない。
チーフが思い出すように、ゆっくり振り返る。
「それよりも・・・こんな解決案はどう?」
そういって、チーフは私の耳にすっぽりヘッドフォンを被せたのだった。
<セクション3>
時代は2053年4月。
私、山本ひろみはNAGASAKIを訪ねていた。
初めての時間旅行は、少し時差酔いを引き起こしたようで、体がまだふわふわする。
「3日間出張してきて。ジョージくんに会って来なさい」
チーフからそういって渡されたのは、1枚のコンサートチケット。
ラブ☆マスターズのチケット・・・のようだ。
「でも、、、これで、私になにしろっていうのよ?」
声優アイドルのコンサートって、、、私にとってまったくの専門外だ。
到着先は、有機的な雰囲気をもった研究室だった。
「お疲れさま。ユグドラシル研究所へようこそ」
たどり着いた先は、研究室の一室。
びっくりしたのは、、、、そこに50歳の私とジョージがいたことだ。
目の前の私が、足元おぼつかない27歳の私を支えた。
寂しげに笑顔を浮かべる彼女。鏡の前にいるようなそんな不思議な気持ち、なんだか他人をみているようだ。
「自分と対話するのも慣れないものだわ。ゆっくり、この時代を満喫していってね」
あっさり去っていく50歳の私。なにか、避けされている気配すら感じてしまう。
「びっくりしただろう。ひろみ」
代わりに残ってくれた、ニホンオオカミ姿のジョージがにこやかに笑って、私はすぐに許された気分になった。
私の時間軸では数年前、過去に渡ったジョージことスクランブル。
しかし、彼にとっては、半世紀以上の旅だったことだろう。
ああ、やっと会えた。
切なさのあまり、私は彼を思いっきり抱きよせた。きつくきつく抱きしめた。柔らかい毛並みがそっと頬をくすぐる。人間でなくたって構うもんか。手が触れられるだけで構わない。
「おい。2人きりじゃないんだから」
慰めるように私を諭すジョージ。ああ実は照れてるな。何もかもが新鮮だ。
「聞きたいことがあるの。『Let It Be』って知ってる?」
しばらくして、シティホテルにいくタクシーの中で、堰を切ったように私は訊ねた。「チーフがあなたに確認しておけっていったんだけど」
「レットイットビー?」
「今回、あなたに与えられた役目だ、って言ってた」
「そうか。まぁ、いちミュージックプレイヤーとして意見を言えば、同じタイトルのビートルズナンバーが有名だな」
さんざん、過去、岡野陽子に歌わされたとこぼす彼。苦労しているんだなぁ、とまじまじジョージを眺める。でも。このヒントだけでは、チーフの解決案を洞察できない。
「今夜は、子守り歌を歌う必要がありそうだな」
ジョージは、私のその言葉に少し頭を傾げたのだった。
<セクション4>
今回は時間旅行は出張であって休暇ではない。
翌朝早く、ユグドラシル研究所にやってきて、メイン端末の前に立つ。
HANAとの通信が可能な研究所と聞き及んで思う。この時代はいろんな意味で歴史のターニングポイントだ。
未来人の私がこの過去にいること。
そして、マークとひながこの時代で結婚式を迎えていること。
この2点だけで十分すぎるほど、未来に与える影響は大きい。
逆に言うと、だからこそ、時間管理局のエキスパート、ワイフォン使いのスギヤマがここにやってきたのだろう。
いろいろと考えることが多い中、一人の研究員が私に昼食を誘って来た。
無精髭のやぼったい男で、やたらゼロコーラが好きという下戸の男性。名簿によると、日下部透といったか。その姿と裏腹に鋭い視点と明瞭な頭脳を持っている。右腕にしたら、頼りになりそうな部下だ。
「所長、何か入りようでしたら、お申しつけください。妻が力になりたいと言っています」
ああ、ひとつ大事な説明を忘れていた。日下部はゾッコンの愛妻家だった。
「妻ももともとは、この研究所の研究員でして。旧姓をチヂワと申します」
そうか。
メタバースの画期的な提案者カナ・チヂワの論文は読み返した記憶がある。ほかでもない、ジョージが育てた2人めの子供だ。言ってしまえば、今回の件は義理の娘が声をかけてくれているようなものである。
「ありがとう。助かるわ。あなたの奥さんをコンサートに誘ってもいい?そして、この時代の流行の服を準備してほしいの」
日下部が笑う。最初からわかって言ったのだろう。
「わかりました。さっそく伝えておきます」
そのとき、持たされた私のスマホ端末が着信した。50歳の私からの呼び出しだった。
「来たわね。少しは時差酔いはおさまった?」
「おかげさまで」私は軽く頭を下げる。
そこには、50歳の私の他に、スラリとした風貌の男が立っていた。
「タカフミ=スギヤマと申します。今回は、探偵「スタンプ」としてこの状況を処理します。お見知り置きを」
軽く私も自己紹介する。
この時代では探偵の仕事をやっている彼は、先にも触れた時間管理局の専門家。当然、その端末としてジョージもこの場にやってきている。
「今回の時間事故は、人為的に起こされた事故であり、すべての責は彼が負う。
HANAが示すリカバリー率は30%。ただし、善処すれば、今回の件はなかったこととする」
「チーフからの提案ですか?」
と私は確認する。
「そうだ。レディ・ヒナからの提案だ」
疑問にひとつ気づいてしまったが、私はそれを飲みこんだ。
<セクション5>
「わーー、すごーーい」
周囲に溢れる人混みに、私は目を丸くしていた。
「ひろみさんは、アニメはお好きなんですか?」
かなが聞いて来て、私は首を横に振った。もちろん、大きく、ダイナミックに。
「いや、全っ然わかんない。オタクについての生態はまーっったく理解できないわ」
コンサート会場は、20世紀末に建設された「長崎ブリックホール」
古き良き時代の名残が残っている。
てっきり、MICE会場が選ばれるのかと思っていたら、そうではなかった。
21世紀中盤にネット設備が整い、この場所の利点があらためて浮き彫りになったらしい。
「観客席、かなり埋まってますね」
まったくだ。とかなの言葉に相槌を打つ。
1000人規模の会場の席はぎっしり埋まっている。確かこれ、ハイブリッドコンサートのはずだよね?
パンフレットを見ると、ライブビューイング会場もいくつかあって。
この時代。素材としての声優市場は想像以上の大盛況。大人気だったらしい。
「思えば、うちの子たちも初恋が二次元で。まったく、空いた口が塞がりません」
若く見えるが40代後半のかながため息をつく。
私たち2人のおばさん会話に、周囲の若者が不審な目を向けて、とっさに私たちは口をつぐんだ。
危ない危ない。
「ほら、ひろみさん。はじまるみたいですよ」
そして、いよいよ幕が上がった。