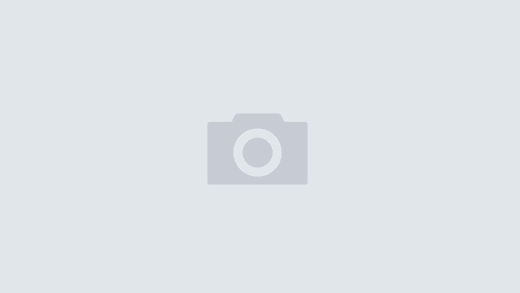西暦2043年3月15日 千々石かなの場合
<セクション1>
私は、千々石かな。20歳。長崎大学データ科学部3年のぴちぴちの大学生。
山口弘幸教授のゼミに所属している。
21世紀初めから爆発的に発展した仮想世界すなわち「メタバース」研究がそのテーマ。
「仮想現実上の恋は、現実のかわりとなり得るのか?」
その検証に私は今、取り組んでいる。
向かいから、紺色のワンピースを着た亜麻色の女の子が手を振った。
「リズ、遅い!」「ごめん!」
私と彼女はチャットを交わす。
私がその娘に会ったのは、古典的な掲示板サイトだった。ブレイクルームに誘われて、そこで意気投合した私たちは、度々、仮想空間で行動をともにするようになった。アバターとはいえ、悩ましいことに私好みの美少女なのだ。ちなみに、私自身も今はフリー。彼氏の美樹本君とは2年越しの恋愛を経て、つい先日破局したばかりである。
今、私たちがデートしてるのは、巨大企業メタ社が開発した仮想世界。
その世界上の噂になっているバーチャルカフェへ私たちはお出かけをしていたところだった。
リズは表情豊かな娘だった。
ようやく飲酒にも慣れた私はスパークリングワインを頼んで話し込んだ。
「あなたはどう思う?」
海産物と春野菜のパスタに舌鼓を打つ。最近の仮想世界を甘くみるなかれ。味も匂いも絶品だ。
「そうだな。流石にそれはないかなって、ボクも思う」
私のアバターが私の仕草を再現する。
ちなみに私のアバターは、現実とは違う中性的な少年のイメージを模している。
一人称を「ボク」と名乗るのは、一種の演技だ。
その虚をつくような言葉がいきなり投げかけられた。
「私、あなたに相談したいことがあるんだ」とリズ。
「何だい?」
「あなたとリアルでお話をしたい」
<セクション2>
どうしてこんなことになったんだろう?
私はVRゴーグルを外して、ため息をつく。
ここはアパートの私の部屋。ジャージ姿の腐女子ファッションで私は現実にかえった。
リアルでリズに会うのは勇気がいるというか。
ため息をつく私。
「まいったなぁ・・・。多分、リズのやつ。あたしを完全に男だと思ってるよなぁ・・・」
一応、断るに断れず、私はクローゼットの中の服を見る。
「可愛いのがいいか、ボーイッシュな感じがいいか」
えっと。
別に私は女の子同士でも恋愛できると思っているけど、リズはそうじゃないだろうし。
今まで聞いた話だと、リズの恋人は生まれてこの方、他の方とはお付き合いしていないらしいし。その上、私自身は美樹本くんと別れた際に、髪をベリーショートカットに切ったばかりだから、中性的に見えなくもないとはいうか。
「どうしたんですか? かな?」
声をかけられて、私は足元のニホンオオカミを見る。小さい頃から私を育ててくれた育児ロボット。スクランブル。
「えっとさ。どうしたらいい?」
「返事したんでしょう?会うしかないですね」
とスクランブル。「案外、うまくいくのかもしれませんよ」
「、、だといいけど」
最後のため息が、思わず大きくこぼれたのだった。
<セクション3>
待ち合わせ場所にやってきたとき、私の目は点になった。
「はじめまして。僕が『リズ』です」
爽やかなテナーのやけに通る声。
目の前の人物は男だった。しかも、口元がまぶしい超絶美形の王子様。
さらさらの髪。スラリとしたスレンダーなスタイル。背丈も頭ひとつ、私より高いだろうか。こぼれるような爽やかな笑顔に、きらりと光る口元の真っ白な歯。
2重の意味でずるい。
美少女アバターで騙しておいて、中身がイケメン王子なんて・・・。
「君だって、男のふりをしてたでしょ?お互い様ですよ」
「うーっ」
イケメン男子がお相手なら、もう少しそれにあったオシャレをしたかった。
今の私の服装は少年のようなジーンズにTシャツ、髪も短く切ったばかりだし、背丈も胸も控えめ。
爪をかみながら、私は王子を睨みつける。
とりあえず、立ち話ではなんなので、近くのお店に入った。
喫茶店かファミレスか、そこのところは覚えていない。ニホンオオカミが入っても差し支えないお店だから、それなりに高価だった気もする。
「あなたの端末をお借りしたいんです。このメタバース上に探したい人がいて」
懐から写真をとり出す。
王子のアバターとうりふたつの亜麻色の髪の女の子だった。
<セクション4>
紅茶とコーヒーを頼んだ私たちは、窓辺の椅子に並んで腰掛けた。
彼の本名は、トーヤくん。婚約者を探している最中らしい。その婚約者というのが、彼が仮想現実で装っていたアバターの少女。亜麻色髪の16歳の女の子。ちなみに、リズというのは愛称で、本名は「エリザベス」。
「で、そのエリザベスさんとやらをスクランブルなら探し出せると」
「ええ。HANAの有機端末のひとつですから」
わん。とスクランブルが答えた。
HANAとは遠い未来に開発される時空を超える性能を誇る超スーパーコンピューター。
それにつながるスクランブルにかかれば、ものの数分で惑星の中から一粒の砂ですら探し出せるとトーヤは話す。
マジか。
チートすぎだろ。私、彼をただの育児ロボットとしてしか思ってなかったし。
「大丈夫。過去。彼の性能を知らないあまり、ミュージックプレイヤーとしてしか使わなかった芸術家もいましたから」
そう言って、トーヤがスクランブルの頭を撫でる。
「間違いなくスクランブルなら、メタバース内に逃げ込んだエリザベスを見つけ出せます。僕と一緒に、彼女を探してください」
<セクション5>
結論から言おう。王子の話した通り、スクランブルの探索は一瞬だった。
スクランブルをメタバース内に接続し、検索させること数分。
検索結果にヒットしたのは2件。ひとつがトーヤが演じていたリズだから、つまり、ひとりに絞り込めたのだ。
そこは日頃、私たちが行くことのない「エリア801」。
無人で、さびれた高層ビル群が立ち並ぶ。
その時、あたりに笑い声が響いた。
おーほっほっほ!
「やっぱり来たわね! 変態誘拐魔!」「ゆうかいま!」
声が高く響き渡って、空中をスクーターが走り抜ける。
スラリとしたワンピース姿の女性と小学生の子供が、ビシッと私を指し示した。
「情熱のリズ・マリコンビ、ただいま再び見参!」
「・・・あれ、本当にあなたの知り合い?」
となりをみると、リズの姿をしたトーヤが頭を抱えている。
「はい。間違いありません。「エリザベス」・・・と「まりんお母様」です。まさか、メタバース内にまで連れてくるとは思わなかった」
半分、および腰のトーヤくん。
くいくいっと、スクランブルが私の裾を引っ張る。
「実は、トーヤさんは、お母様が怖いんです」
なるほど。
「ねえ、エリザベスさん・・・だっけ?ちょこっと、話があるんだけど」
話が進まないので、私が言葉を挟む。
きょとんとして、リズ・リミコンビが私をみた。
スクランブルが無口のまま、待機モードに入っている。
とりあえず、話せることは話しておこう。
「あなた、トーヤくんの婚約者なんでしょ?どうして逃げ続けるの?」
<セクション6>
「・・・」
私の言葉にエリザベスが顔を真っ赤にして黙り込む。
「まんざらでもないんでしょ? だったら、一度、トーヤくんとやりなおしてみようよ?」
現在の私の年齢は20歳。少しは恋について知っているつもりだ。
「だって、結末のわかるそんなゲームなんてつまらない。だって、どんな人も生まれた時に将来の結婚相手がわかっていたら、逃げ出したいに決まっているわ」
「そうかなぁ。恋愛はプロセスにこそ意味があるんだと思うけどな」
「・・・」
思わずこぼした私の一言に、少女は天啓を受けたようだった。
「ゴールより、途中経過が面白い・・・?」
「そうともいうわね。どう、少しは彼との関係を見直す気になったかな?」
ぽつりぽつり、空から雨が降ってきた。
たちまち、画面がノイズでいっぱいになる。まるで世界が泣いているようだ。
そして、不意にメタバースとのアクセスが途切れた。
<セクション7>
世界的なバグだった。
翌日、詳しい調査結果が出るまで、数日間メタバースへのアクセスは停止する通達が大学に流れた。原因は、メタバースを管理するプログラムの不具合だった。サーバーへの負荷がかかりすぎたのだろうか。憶測は飛び交う。
他の雑務をこなすうち、数日間が過ぎ、私は再び、現実世界のトーヤくんに呼び出されていた。
「残念だったわね。あの雨がなかったら、もう一歩で和解できそうだったのに」
「いえ。十分です。ありがとうございました」
王子がまいったように、頭を掻く。「ただ、お礼をしたいと思いまして。あなたの研究に役立つんではないかと」
「?」
「メッセンジャーアプリに地図を入れておきます。タグが示すポイントに実際に足を運んでみてください」
さっそく、二次元バーコードが送られてきた。
「これまでありがとう。機会があれば、また、お会いしましょう」
そういって、トーヤくんは去っていく。
名残惜しいなと思ったけど、心の中で幸せになるんだぞ。とエールを呟いた。
<セクション8>
トーヤくんのQRコードが指し示す場所。すなわち「ユグドラシル研究所」に私はやってきた。
「あ! 日下部先輩っ!」
懐かしさに溢れたその白衣姿を見つけて、私は驚く。ボサボサ頭に、無精髭。野暮ったいその奥の優しい目。2年前、私の初恋のAIを作り上げた大先輩。
「就職直後に引き抜かれてね。今は、大型コンピュータの端末を取り扱っているんだ。かな君にも案内するよ」
ん?
違和感を感じた。というのも、日下部さんは今まで、私を呼ぶ時は苗字で読んできたはずだ。
「この研究所の所長は不在で、僕が代理を務めている」
日下部先輩が案内したその施設は、清潔でありながら自然と調和した不思議な有機空間。まさしく世界樹という表現がふさわしい。
「素敵な職場ですね。今、先輩はここで何の仕事をしているんですか?」
「メタバース世界の構築だよ。住人のAIを作って、メタバース内に住まわせているんだ」
もしや? と気づいた。というか、気づいてしまった。
「・・・もしかして、先輩。最近、女の子の2人組を作りませんでした?」
「さすが。相変わらず勘がいいね」
ぺろっと口を出す。「君が先日会ったリズ・マリコンビは、僕が本人そっくりに作り上げたAIだ。本人は別の時代にいる。最初から、トーヤくんもそれはわかっていたらしい」
日下部先輩は、研究室のラウンジに私とスクランブルを招いた。
昼下がりのカフェ。陽光が穏やかだ。
すっと、グラスが運ばれて、よく冷えた琥珀色のジュースが運ばれてきた。
「健康に悪いですよ。先輩。相変わらず、ゼロコーラなんて」
「まあね。僕はお酒を飲まないから、これくらいしか楽しみがなくて」
穏やかに笑う。
卒業祝いで初恋の相手からのサプライズに涙した先輩とは何かが違った。
「君の研究について、僕なりの見解があるんだ」
「ああ、メタバースでの恋愛は果たして恋なのか、ってやつですね」
きっと、トーヤくんが話したんだろう。
「で、見解ってなんです?」
「恋愛はプロセスだ、、、って、かなくん自身が言ったじゃないか。ずばり、それが答えなんじゃないかな?」
「・・・あ」
気付かされた。そうか。
たとえ、肉体的接触がなくても、人が学び合えるとしたら、そこに恋愛は成立する。すなわち、メタバース間での恋愛も立派な恋愛として成立する。
「仮説だけどね。それに今回のトーヤくんとエリザベスさんの恋愛をエビデンスに、研究を進めると面白いと思うよ」
さすが。と舌を巻く。
「ありがとうございます! ・・・でも、先輩。なんで私にそれを?」
「君は、僕の人生における共同研究者だもの。助け船くらいは出すさ」
「・・・・・・・え?」
耳を疑う。難しく言っているが・・・。それってつまり。
「ちょっとちょっと、いくらなんでも、それはあり得ませんよっ!」
「まあまあ、未来がそう決まっていても、今の僕らは他人でしかない」
「先輩っ!からかわないでください」
「へいへい」
先輩はイタズラ顔で、ゼロコーラを口に運んでいたのだった。
数年後、私は大学院を卒業してユグドラシルに就職し、苗字も『日下部』姓になるらしい。
メタバース内に生きる多くのAIたちの行動を構築する。恋愛発情症候群のアルゴリズムはユグドラシルのコンピューターを使って解析され、論文として発表されて、世界を震撼させる。
ーーとか、言われても。
「未来はともかく、今は学ぶしかないですよ。恋も学問も」
「そうよねぇ」
スクランブルと愚痴をこぼす私。
さて、そろそろトーヤくんの思いは本物のエリザベスさんに届いたころだろうか。
私は願いながら、ユグドラシル研究所を後にしたのだった。