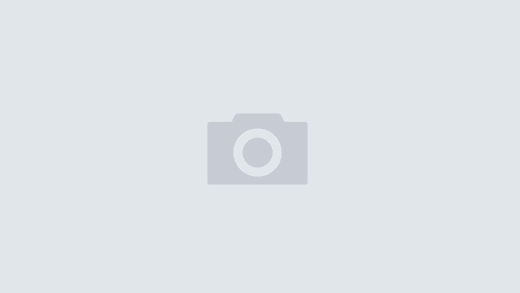第1話
夕暮れのトラックを走る。ただ、走る。
ゴールの見えないテープをめざして、動かない風をすり抜けて、かわすようにかきわける。がむしゃらにもがく足がやたらと重い。100メートルがはるか遠い。
「全然、ダメだ!どうした。もう1回!」
やっとこさ、ゴールを切る僕にコーチの怒声。
いったい、何回、走らせるつもりだよ。わかってるさ。風に乗れなかったことくらい。
「はい、ふうたくん」
いつのまにきたのか、肩で息をする僕の後ろから、マネージャーのひよりちゃんがスポーツドリンクを差し出した。
「ん」僕はボトルを取って、少しずつ飲み下す。ゆっくり、ミネラルと水分が喉を落ちる。
「ふうたくん、記録のび悩んでるね」
「わかってるよっ」
言われて、あせりから声をあげる。ひよりちゃんは肩をすくませて、キャプテンのやまちゃんにドリンクを渡しに向かっていた。
原因はわかってるんだ。川浜コーチとの相性が悪すぎるんだ。
以前から指導してくれた静香先生が産休に入り、ピンチヒッターで新しいコーチに変わったのが最近のこと。何でも、将来が期待される部のために、名門から引き抜かれたエリートらしい。
ところが、僕との相性が悪かった。見る間に記録は落ちた。僕の受け止め方に問題があるのか。将来のためにも、そして高校生活の集大成のためにも、僕には結果がいるんだ。他の部員たちはちゃくちゃくと記録を伸ばしている。このままだと記録どころかレギュラーの座さえ危ういだろう。
次の大会は6月。とても、間に合う気がしなかった。
第2話
中間テストがかえってきた。
結果は相変わらずだ。数学と物理はまあまあだったけど、英語と国語が壊滅的に悪い。文学は行間を読むことが大切と言われるけど、書いてない文字の間にどんな意味を見つけようと言うのだろう。そもそも、問題の意味そのものが僕には理解不能だ。
「ふうたさま~ぁ、どうだった?」
クラスメイトのいつきが帰ってきたテストをのぞく。僕は見えないよう裏返して隠す。
「どうせ、テストの受け直しに、補習に行くんだろ? なんなら、ついていってやっても構わないんだぜぇ?」と、いつきがからかう。
「なんとか、赤点は回避してるさ。お前とくらべるんじゃねーよ」と僕。
「なんだとぉっ!表に出ろ!」
周囲がくすくすと笑っている。いつきと僕の喧嘩は日常茶飯事。
なにしろ、保育園からのよしみだ。周囲をわきまえた喧嘩の仕方は知っているし、それは、いつきだって同じ。いい意味で、腐れ縁の僕たち二人が、どんな形であれ仲がいいことはみんな周知の事実だから、担任の先生はじめ他の同級生も真剣に取り合わない。僕は気にいらない人間とは、最初から一切の口をきかない。だから、いつきと話ができるってことは、お互い認めているってことでもあった。
とりあえず、ここからは大会に向けて、部活にまっしぐらだ。
「ふうたくん、女の子が呼んでいるよ」
クラスの女子が、僕に声をかける。見れば、別のクラスのひよりちゃんが、教室の扉の前に迎えにきていた。僕は「ん」とだけ応えて、ひよりちゃんのもとへ向かう。
「・・・ねえ。ふうたくん。あの子にお礼くらい言った方がいいよ?」
「必要ないさ。だって、日常だもの」
「せっかくあなたのために声かけてくれたんだから、感謝の気持ちは伝えないと。友達いなくなっちゃうよ?」
「ん」気の無い返事を再度、繰り返し、僕はさっさと教室を出た。
第3話
その日とうとう、転機が来た。
「もういいだろ!記録が伸びないのはコーチのせいだ!」
僕は10本以上も繰り返したダッシュのあとで、川浜コーチに怒鳴り返した。
周囲が驚いたように、対立する僕たちを見守る。上下関係の厳しい体育部で、指導者に歯向かうことがどういうことかわかっていた。でも、僕にとって、意味のわからない練習はもう限界だった。
「やめてやるよ!こんな部!大会にも顔出さない!」
からっぽの部室で着替えた僕を、ひよりちゃんとやまちゃんが心配そうに待っていた。
「ねえ。ふうたくん」
「知らん」
僕は悪態をつく。思い出すだけで、はらわたが煮えくりかえる。
ひよりちゃんが体を震わせて、僕を見る。その震えが示すものを、その時の僕にはわからなかった。
「ふうた。本気で辞める気か?それで本当にいいのか?」
やまちゃんが口を開く。
僕、ひよりちゃん、やまちゃん、いつきは、子供の頃からの付き合いだ。その頃から、やまちゃんは頼り甲斐があった。
「幼いころから、夢中になってきたじゃないか。さあ、コーチに一緒に謝りに行こう」
「誰が行くかよ」
まったく、こんな時もやまちゃんは世話好きだ。どんな時も、部のみんなのことがわかる。人の気持ちが汲み取れない僕と大違い。劣等感が苛んだ。
何度も何度も言葉を拒む。
やまちゃんとひよりちゃんが顔を見合わせた。
ぼくは着替えの入ったバックを背負い、自転車に飛び乗る。逃げるようにペダルをこぐ。風を切って、自転車が走り出した。
第4話
学校が味気なかった。
いつきが仕掛けてくるちょっかいも、今では、全てが煩わしい。
すべての授業が終わると、教室にひよりちゃんが迎えにきた。それをすり抜けて、僕は放課後をゲームセンターで過ごした。
最近は部活で時間がとれなかったから、ひさしぶりのゲームセンターは新鮮だった。どうせこうなるんなら、どうして走ることを早くに諦めなかったんだろうか?
最初に人生の結末を知りたい。そして、この世から、無駄な努力を全部なくそう。
大会まであと3日。
それでも、ひよりちゃんは迎えにきたけど、その日も僕は無視してのけた。
今、調整をしないということは、完全に大会当日へのコンディションづくりを諦めるということ。もう、大会への未練はまったくない。記録が伸びないのに走ることにどんな意味がある?
「なあ、おい」
ゲームセンターで隣に立ったいつきが僕に話しかける。
「いーのか? 大会近いんだろ?」
「知らねーよ。すべてコーチが悪いんだから」
「ふうん」
いつきが気の無い返事で応えた。
しばらく時間を潰して帰宅すると、父親が僕を待っていた。神妙な表情だ。
「部活、、、休んでいるんだって?先ほど、指導者の方がいらっしゃったんだが」
あの川浜コーチめ。姑息な手を。
「知らねーよ」
僕は、口癖を繰り返し、自分の部屋に逃げ込む。スマホを家のWi-Fiに繋ぎ、無料ゲームをタップした。繋がった瞬間、イライラが消えて、僕の気持ちは穏やかになった。
幼いころからの唯一の取り柄をやめたんだ。もう学校に行く意味もない。すべてが「知らねーよ」だった。すべてが他人のせいで、あらゆる些事が他人事にように感じられた。
第5話
やがて、学校に行くふりをして、僕はゲームセンターに通い詰めるようになった。大会当日も会場にすら行かなかった。ひよりちゃんにも、やまちゃんにも会わなかった。たまに、ゲームセンターで学校帰りのいつきに出くわした。
ある日、いつきが僕に声をかけた。
「もったいないぞ。どうして、学校に行かねーんだ?みんな心配してるぞ」
まったく、お節介というか。
「知らねーよ」
僕は、ゲームに熱中するふりをして、繰り返した。
「ふうたくん」
声がして、振り返る。バツの悪そうな顔をした、ひよりちゃんとやまちゃんが立っていた。
多分、いつきが連れてきやがったんだ。
「走るのをやめる決心はわかった。でも、学校には行かないと・・・」
やまちゃんが、ぼくに声をかける。
「知らねーよ。優等生のやまちゃんに、僕の気持ちがわかるかよ」
「ふうたくん!」
ひよりちゃんが、ぼくとやまちゃんの間に割って入った。
「どけよ!」
ぼくが突き出した手に押されて、ひよりちゃんが倒れた。
空気が固まった。
「おい」
それまで黙っていた、いつきが僕の襟首をつかんだ。
「お前がどーなろうと知ったことじゃないけどよ。ひよりちゃんに暴力振るうのはおかしいだろ」
1発、いつきの正拳が僕の頬に入った。
第6話
そこからは、めちゃくちゃだった。
逆上したぼくといつきの喧嘩は、警察を呼ぶほど白熱した。
僕も不満が溜まってた。
だれも僕の気持ちをわかってはくれない。
当然だけど、僕といつきは1週間の自宅謹慎になった。
この学校にしては、穏やかな措置だった。本来なら、退学になってもおかしくない。そうならなかったのは、やまちゃんとひよりちゃんが場を収めてくれたことと、僕ら2人の関係を知っている学校側の配慮のおかげだった。
数日後、自宅に1人の来客があった。
休んでいたはずの静香先生だった。
「あ、、、」
僕は、言葉を失った。
いつもなら、結果を出すたびに一緒に喜んでくれた静香先生。ようやくやっと、自分のしでかした事の大きさに気づいた。帰ってくる彼女のことも考えず、積み上げてきた数年間を捨てて、逃げて、仲間にも暴力を振るった。
なんとか、逃げるように言葉を探した。
「先生、、、産休もういいんですか?」
「ダメに決まっているじゃない。こっちは1週間前に出産したばかりの新米母さんよ」
弱々しい顔で笑いながら、コーチがこづく。
「でも、今はそんな場合じゃないでしょ。ドクターストップを振り切ってきたわ」
目頭が熱くなった。
川浜コーチから謝罪を受けたと静香先生は話した。価値ある才能を潰した責任を取りたいと。周囲は猛反対したそうだ。僕のいない穴を埋めたのは、驚いたことにやまちゃん。過去最高の記録を残して、エースの代役を務めあげ、県大会2位に名を残した。当然、短期間で逸材を育て上げた川浜コーチを学校が手放すわけがない。
悔しかった。そこにいたのは僕のはずだった。
「ううん。あなたは、もっと上に行けるわ」
言われて驚いた。
「川浜先輩とあなたはスタイルが似てるからね。うまく噛み合えば、全国区の成績が狙えると思うの」
初めて聞いた川浜コーチの内輪話。
「、、、」
涙が止まらない。静香先生の優しさがひたすら痛い。
今さら、すべては取り戻せない。
「終わったと思ってる顔ね」
さすが静香先生。僕の考えが見透かされてる。
「違うんですか?」
「最後まであきらめない。私が、最初に教えた事でしょ」
肩を叩いた手は、産後の女性とは思えないほど、心強かった。
第7話
「なんで、僕がこんなことやらなきゃいけないんだよ、、、、!」
謹慎が解けた1週間後。
僕はとある山小屋に住むひとりの老人の世話になっていた。
名前を「ゲンゴロウ爺さん」。静香先生や川浜コーチたちを指導したかつての名指導者だと聞いている。
『あなたの答えがそこにあるわ』
と静香先生。出した休学届けは1ヶ月。それ以上の休みは、受験に差し障るとの判断だ。
山小屋は、登山道から離れた深い森に立っていた。バスも1日に数本くるかこないかの山奥だ。バスの終点から、さらに歩いて30分。簡素な山小屋が、ゲンゴロウ爺さんの家だ。
そして今、僕は、風呂のために、川から水を汲んで運んでいる。川と山小屋との距離はゆうに500メートル。一体、何回、往復する必要があるのだろう。考えるだけで気が重い。
爺さんは、外出中だ。今夜の夕食の食料を調達に出かけたんだとか。
「なにせ、来客は久しぶりだからの。腕によりをかけるぞい」
風呂が水でいっぱいになる頃を見計らって、ゲンゴロウ爺さんが帰ってきた。
手に持ったザルに、キノコと野草と毛をむしったウサギを掴んでいた。ウサギは罠にかかっていたとか。どの光景も僕にとって、目に新しい景色だった。
薪で沸かした五右衛門風呂から上がって、ほっと一息。
山奥だからだろうか。真夏だと言うのに、日が暮れると同時に冷え込んだ。
炭が燃える囲炉裏。天井から吊り下げられた鉤に、鍋をひっかけてある。
「静香からは聞いとるよ。伸び悩んでいるんだって?」
僕は事情を説明した。話せば話すほど、場違いな場所にやってきた後悔が胸に去来する。電気も水道もガスもない。こんな場所に来て、僕に何が見つかるというのだろう。
囲炉裏越しのゲンゴロウ爺さんは、穏やかな顔を浮かべている。
「そうか。川浜の坊主とやりあったか」
爺さんが楽しそうに笑った。真っ白な歯がこぼれる。
「おそらく、走ることでしか答えが出ないことを伝えたかったんじゃな」
なんだそれ。拍子抜けした。
そんな簡単なことだったら、口頭で言えば済むじゃないか。
ゲンゴロウ爺さんが、鍋をすくって、僕に差し出した。
腹が鳴った。
そういえば、どっぷり日は暮れたのに、まだ、夕食も食べてない。受け取った皿は、やけに熱い。無言ですする。空腹に、キノコ鍋が染み渡る。
「食べたら、寝ろよ。明日は早いぞ。体を冷やさんようにな」
第8話
翌日から、僕はあっちこっちに連れ回された。
重装備を入れたキスリングザックを担いで、何度も山道を練り歩いた。
陸上部で鍛えたはずの足腰が、とことん悲鳴をあげた。
一方で、爺さんは健脚だ。疲れた様子もなく、時に立ち止まって風を確認しながら、軽い足取りで軽快に歩を進める。
昼食のおにぎりをかじりながら、自分にはフィジカル的な問題があることを再確認した。足腰が決定的に弱い。こんなんじゃ、成績なんて残せるわけがない。1日に山道を20キロは歩いたんじゃなかろうか。背中の重量はすぐに慣れた。筋肉痛も3日目で取れた。でも、厳しい山歩きが続く現実では気休めに過ぎなかった。
逃げよう、と決心したことには1度じゃない。
何度も荷物をまとめて、夜間に逃げる。でも、無理だった。
ゲンゴロウ爺さんは、夜になると、決まって終点のバス停で、いも焼酎のお湯割りを傾けているのだ。何度も出くわしたから、多分、それが日課なのだろう。
バスを待とうとすると、爺さんがニヤニヤ顔をするのだ。
「坊主、逃げるのか?」
僕も自分が恥ずかしくなって「ただの散歩だよっ!」と意地をはる。
終いには聞いた。「ジジイ、ここでもし僕が逃げたら、どーするんだよ」
楽しそうに、爺さんは言った。
「いいんじゃないか?アスリートには、臆病風も必要じゃよ」
それを言われると、自分が急に情けなくなって、しぶしぶ道を引き返すのだった。
今、思うと、たとえ逃げたとしても、ゲンゴロウ爺さんは責めなかったんじゃないかって思う。その意味で、爺さんはとんだ曲者だったし、優しかったし、お節介焼きな人だった。
季節は初夏。僕が山小屋に来て、3週間が経とうとしていた。山道でも、登山客に何組も出くわしたし、空も入道雲が昇るようになった。
「よう、坊主。そろそろ、走ってみたいとは思わんか?」
ゲンゴロウ爺さんが急に、話題を向けた。「そろそろ、体も軽くなったし、もうきっかけもつかんだ頃じゃろ?」
そう言われても、僕には検討もつかなかった。きっかけどころか、いまだに何が何やらわからないまま、がむしゃらな日々が続いていただけだった。
変わったことといえば、川浜コーチに対する負の感情がどうでもよくなってきたくらいか。あまりに川浜コーチを「坊主」よわばりするものだから、エリートの肩書きすらも彼の強がりに思えてきた。実際、爺さんからしてみれば僕と川浜さんは同じ次元の「坊主」でしかないのかもしれない。
「走ってみたいかは知りませんけど、山歩きを休めるなら、なんでもいいっすよ」
僕もゲンゴロウ爺さんと暮らした数日間で、くったくなく話せるようになっていた。
何せ、ゲンゴロウ爺さんは、よくしゃべった。
それに応戦しないと、いくらでも山歩きが過酷になった。コミュニケーションは命懸けだった。
第9話
翌日早朝、僕らは、山を降りることになった。
今回は、爺さんも一緒だ。
静香先生の旦那さんが、車で僕らを迎えに来た。
来た先は、僕らの高校が練習に使っている陸上競技場。もしやと思ったけど、そのもしや。
僕は固まった。
そこには、やまちゃんとひよりちゃんと、川浜コーチがいた。
3人とも表情が厳しい。
車の中で聞いたんだ。先日、全国大会を終えて、やまちゃんたちも引退をしたんだそうな。
「先生、本気ですか? 県大会2位の山崎と、その落ちこぼれを競わせるなんて」
川浜コーチが爺さんと僕を挑発する。
あ、このクソコーチ、開口一番、言うことがそれかよ。
「まあ、そう粋がるな川浜。こいつは骨のある逸材だぞ。何せ、岸田源五郎の愛弟子だからの」
ゲンゴロウ爺さんも応戦する。
というか、勝手に僕って、爺さんの愛弟子にされちゃってるけど。
僕は久しぶりに軽装になって、やまちゃんの隣に立った。
「ふうた、、、随分、体を絞ったんだな?」
やまちゃんがぼそりと僕に言う。
「そうか? まだまだ、足りないと思うけど」
履き古したランニングシューズに足を通す。
久しぶりの感覚、足が馴染む。立ち上がる。確かに体がかなり軽い。
スタート前の緊張感、、、しばらくぶりだ。
初夏の空気を確認する。
今は、風はない。でも、プレッシャーも感じない。ただ、走ればいい、単純な思考に感覚を重ねる。
、、、と、ふと我に帰った。
風を待っているだけじゃだめだ。もっと感覚を研ぎ澄ますんだ。
クラウチングスタートの体制をとる。距離は100メートル。
さあ、県大会2位との真剣勝負の始まりだ。
僕は合図と共に、スタートを切った。
第10話
周囲は、結果に呆然となった。ゴールを切って、肩で息をする。
体一つ。僕は、やまちゃんより早くテープを切っていた。
「10秒01・・・です」
ひよりちゃんが驚いたように、ストップウォッチの記録を読みあげる。
高校記録タイ。まあ、いろいろあって今回、正確な公式記録ではないけれど。
一方で、僕の心は久しぶりの感覚に心躍っていた。記録なんてどうでもよかった。やまちゃんと一緒に走るのが楽しかった。
そう、楽しかった。
もっと、走りたい。もっともっと、とわくわく心が躍る。
気がついたら、やまちゃんが右手を差し出していた。
僕も笑顔でその手を握り返す。
「どうじゃな?川浜。往年の自分を重ねられたか?」
とゲンゴロウ爺さん。
「・・・一体、どんな魔法を使ったのやら」
そういうコーチの顔にも悔しさは感じられない。
「川浜。あとはお前さんの手で、一人前に仕上げてみせろ」
ゲンゴロウ爺さんが信じられない一言をはなった。
「ふうた、ひとつアドバイスじゃ」
思わず、爺さんを凝視する僕。「奴が苦言を言ったら、こう返せ。『僕はおねしょはしませんでした』と」
「岸田先生! 私の生徒に何吹き込んでるんですか?!」
信じられないことに、あのエリートコーチが慌てふためいている。
ふうん。川浜コーチって意外と子供じゃん。
そう思うと、急に身近に思えてきた。今までのスパルタにだって、きちんと理由があったわけだし。
"川浜先輩とあなたはスタイルが似てるからね。全国区の成績が狙えると思うの"
静香さんの言葉が脳裏をフラッシュバックする。
そして。
僕は、今でも、その後の自分の行動が信じられない。
その時の僕は、自主的に頭を下げて、こういったんだ。
「川浜コーチ。お願いします。あなたのスタイルを、僕に学ばせてください」
第11話
9月。3年生の授業は、クラスがバラバラになって、大学受験の体制に入る。
僕は、数学と物理を生かした国公立を目指していた。
3年生になって授業を落とした2ヶ月をフォローすることは難しかった。
というか、今でもまったく理解できてない。
その上、授業終了後は2時間のトレーニングだ。
勉学も運動もともにやりながらは、きつかったけど。数ヶ月前の空虚さはそこにはなかった。
いつきともすぐに和解できた。
会うなり、一気に高校生活が戻ってきたような居心地の良さがあった。いつきは不作法で困った奴だけど、それでも青春の1ページには欠かせない存在だった。先に大学への推薦入学を勝ち取ったやまちゃんが、僕といつきの家庭教師を務めてくれて。おかげで、点数はいくらか伸びた。まあ、どうしょうもないときは、笑ってごまかすしかないけど、それまでは諦めずトライする。ひたすら繰り返す反復練習。過去問を徹底的にさらう毎日が続いている。
「ねえ、女の子が入り口で待っているよ?」
女子が、ぼくに教えてくれる。きっと、ひよりちゃんが迎えにきたんだ。
「サンキューな」
僕は、教えてくれたその女の子に一言返すと、僕はひよりちゃんの待つ教室の外へと向かった。
「ふうたくん、変わったね」
ひよりちゃんが、ぼそりと並んで歩く玄関まで一緒に歩を進める。
「悪いな。マネージャー引退したのに、練習に付き合わせて」
「・・・好きでやっていることだから」
うつむいたまま、ひよりちゃんが答える。
部活は本当なら、僕もひよりちゃんも引退なんだけど、特別に新人戦に向かう2年生とともに走っている。
目標があった。
10月に開催される大会を目指す。とりあえずは、今月の地方予選の上位通過。ライバルが多くて面白そうだから、成人枠での出場だ。
それは、夕焼けの綺麗な、部活の帰りのことだったと思う。
「最近、走るのが楽しそうだね」
練習と勉強で遅くなることが増えたので、ひよりちゃんを家まで送るのが日課になっていた。
「うん。そりゃあ、楽しいさ」
急に立ち止まって、ひよりちゃんが僕を見た。少し、言葉をためらっているようだった。
「あのね。相談があるんだ。聞いてくれる?」
ひよりちゃんが言葉をきりだした。彼女がこんなことを言うのは、生まれてはじめてこと。そして、次の言葉は、さらに考えもしなかった一言だった。
「私、告白されたの。どうしたらいい?」
第12話
「ひよりちゃんに告白したのは俺だ」
3日後、信じられない真相を語ったのは、やまちゃんだった。
僕は言葉に詰まった。
その場で、一言も気の利いた言葉を発することができなかった。よかったな、とか、頑張れとか。幼馴染の初恋を応援するエールのひとつでもあったら格好良かったけど、実際出たのは戸惑いとうろたえだった。
なに今頃、後悔してんだ。当たり前じゃないか、いつも部活でもやまちゃんとひよりちゃんは一緒だった。気づかないバカは僕くらいだ。
やまちゃんはすごくいい奴だ。頼もしくて、かっこよくて、根性があって、僕よりも周りから信頼されてて。走るスピードは、今は僕の方が上かもしれないけど、それでもまだ成長期の僕たちだ。いくらでも記録は塗り替えられる。追い越されることも当然あるだろう。走るのは、努力できる。ノウハウだってたくさんある。でも、人の気持ちにはどんな神様も手を出せない。
「だめだ。もう1回!」「はい!」
放課後の僕のトレーニングに、川浜コーチが怒声を上げる。
そばで見守るひよりちゃんの顔も心配そうだ。なぜか、気持ちに気づかれるのがカッコ悪いように思えてしまう。すぐに手に届くところにいるのに、ひよりちゃんとの距離は遠かった。
ひよりちゃん、やまちゃん、いつき、僕。
保育園時代からのこれまでの4人の形は、ずっとこれからも同じだと思っていた。
今日も練習の帰り道、先をいくひよりちゃんと2人きり。
「やまちゃんには、返事したのかよ」
「・・・え?」
ひよりちゃんが驚いたように、僕を見た。「どうして、それを?」
「本人から聞いたんだよ。・・・頑張れよ。僕が言えるのは、それくらいだ」
ぼそっとこぼした僕の言葉に、ひよりちゃんの驚いた顔。
曇って、歪んで、たちまち、ひよりちゃんは泣き出していた。
今更、気づいてしまった。ひよりちゃんは僕を好きだったんだ。
第13話
その夜、電話で呼び出された。夜の公園。街頭のベンチで、やまちゃんが待っていた。
「なんだよ、こんな夜更けに」
自転車を止めて、やまちゃんの前に僕は立つ。
「・・・」
やまちゃんは話さない。今年の秋は深まるのが早い。空気が少し肌寒い。
途中で買った缶コーヒーで手を温める。
「ひよりちゃん、今年中に東京へ越すんだ」
いきなりのやまちゃんの洗礼に僕は驚く。「ご両親の仕事の都合らしい。卒業まで、籍はこの高校に残すそうだけど」
今は9月。残された時間は、あと4ヶ月しかない。
「なんで僕にそんなことを?」
「さっき、涙まじりの電話があった。お前。ひよりちゃんを振ったんだってな?」
そんなつもりはなかったんだけど、ひよりちゃんはそう受け取ってしまったらしい。
「誤解だよ。僕は、やまちゃんとの恋愛を頑張れって・・・」
「フェアプレイはもう懲り懲りだ!どうせ俺じゃお前に勝てないんだ!」
日頃、穏やかなやまちゃんが声を荒げた。「恋も走りも、いつも、ふうたは特別だ」
僕は、ただただ気圧されていた。
気づいたんだ。
そうか。優等生でも、心細いながらに踏ん張っているんだ。
「なあ。・・・やまちゃん。賭けないか?」
僕は、右手の缶コーヒーを差し出す。「僕が、今度の大会を勝ち残れるか、残れないか」
「そりゃ、いくらなんでも賭けが成立しないだろ。お前の出るのは成人大会だぞ?」
「僕は勝ち残るよ。そして、絶対、ひよりちゃんを迎えに行く」
ビックマウスなのは、わかってる。
可能性が限りなく、ゼロに近いのもわかっている。
でも、僕は、走ることしか取り柄がない。だから、これで運命と勝負する。
「・・・予選通過できなかったら?」
やまちゃんがおどおどと、言葉をつなぐ。
「僕は、一生、ひよりちゃんのことを追わない」
「わかった。絶対に、負けんなよ」
「どっちを応援してんだよ?」
苦笑しながら、やまちゃんは僕が差し出す缶コーヒーを受け取った。
第14話
大会3日前、ひよりちゃんと競技場に着くと、珍しく川浜コーチが準備運動をしていた。
周囲には2年生のギャラリーがずらり。
僕も上着を脱ぎながら、ゆっくりストレッチを開始する。
「おい。今度の日曜、県予選だな?」
川浜コーチが声をかけた。
なんだろう。この雰囲気。試合の時の空気感に似て、ピリピリとしている。
2年生の顔もイキイキしている。あれは、何かを楽しみにしている顔だ。
「何やってんすか。コーチ。若作りはほどほどにってゲンゴロウ爺さんが言ってましたよ」
くすくすと笑う2年生。
そして、あろうことか川浜コーチも一緒に笑ったのだ。
「ふうた。仕上げだ。今日は俺と勝負しろ。一度、お前と走ってみたかったんだ」
川浜コーチの年齢は42歳。
現役時代、優秀な事業団の選手で、引退は29歳だったという。
数えれば引退して13年。運動不足のアラフォーには、元気いっぱいの現役高校生の相手はこたえるだろう。でも、あの気合の入れようは、かなり本気のようだしな。
「はいはい。少し待っててくださいね」
諦めたふりをして、準備する。
でも、と思い当たった。勝負に年の差は関係ない。
実際、ゲンゴロウ爺さんとの山歩き。僕は1度も70歳をすぎた爺さんに勝てていない。加齢で体力は落ちても、その分、駆け引きが巧くなる。まして、僕の手のうちは全て知られているから、体力と経験値を同じ天秤にかけるべきではない。
僕は何をつかんだろう。僕がコーチに勝てる何か。
イメージをしっかり作る。どんな勝負になるか、どう出し抜くか、逃げ切るか。空気は湿気を帯びている。若干、地面のグリップは強いはずだ。靴紐は強めに。足はいきなりの運動に悲鳴をあげないようにほぐしておく。ストロークは長めにとろう。歩幅の大きな相手と渡り合うには、多少の無理が必要だ。軽くジョグを15分。よし十分、体は温まった。
僕と川浜さんはスタートラインに立った。
川浜さんのスタートダッシュは、タイミングピシャリ。とても高校生には真似できないロケットスタートだった。あれよあれよと、背中が見える。
僕は焦った。しまった。一計、はめられた。
最初から川浜さんはこれを狙ってたんだ。
ここで背中を追うのはダメだ。一見、距離が縮まっていくように見えて、実はこのペースは僕の本来のペースより遅いのだ。
今から、主導権を取り返せるか? 間に合うか?
集中して目を閉じた。
今、風はない。だから、僕が風になるんだ!
ゴールを切る。2年生の歓声が、僕の耳に入った。
「完敗だ。なかなかの走りじゃないか」
ヘトヘトのコーチが破顔した。勝負は、紙一重。僕の逆転勝ちだった。
「こちらこそ、勉強になりました。相手の心理をつくあたり、流石っすね」
「そりゃあ、経験の差があるからな。・・・それにしても、さっき目を閉じたのは何故だ?」
よく見ている。僕は舌を巻いた。
「ゲンゴロウ爺さんの猿真似ですよ。山歩きの時、よく風を確認してたなぁって。
僕は試合直前、その時の『いい感じ』につながるように流れを組み立てるんですけど、爺さんはもっと積極的にそれをやってて。参考にしました」
「まさか、あの不利な状況下、一瞬でイメージを立て直したのか?」
コーチの顔が驚いた。
2年生は首をかしげてる。そりゃあな。こんなこと言っても、意味がわからないか。
「さすが、本物の岸田源五郎の愛弟子だ」
外野がざわついた。
気がつかなかった。何人か、観客に大人が混じっていたのだ。
後で知ることになる。
それは川浜コーチの紹介で、この勝負を眺めていた実業団のスカウトたちだった。
第15話
時は、それから32年後。2066年10月吉日。
居酒屋「いつき」にて。
「やまちゃん、いらっしゃい」
店主はのれんをくぐった一人の壮年の男性に声をかけた。
やまちゃんと声をかけられた男性はひとり、姿勢を崩さず、カウンターに座る。
常連なのだろうか、店主と親しい。
店主が差し出すおしぼりで、顔を拭きながら、男は鞄を傍においた。
ビールと枝豆が、ごく自然にカウンターに並ぶ。
「いつき、知ってるか?」
店主は言われて、にやりと笑い、壁に貼った新聞を指差す。
スマートフォンが常識となった日常だが、こういった味の出る演出は紙にしか出せない。
「もちろん。ふうただろ?」
誌面では、コーチジャケット姿の厳しい顔の男性を、数人の体格のいい若い選手たちが取り囲んでいる。
「ニュースに出たんだよな。今をときめく名門 四菱造船の名将だ」
白髪混じりの頭をぺちゃんとたたき、やまちゃんはいつきが差し出すジョッキに一口つけた。
枝豆をつまんで、ため息をつく。
「あいつは、昔から特別だ」
やまちゃんがこぼした。
「あのふうたがか? 俺は、あいつと殴り合ったことしか思い出せないけどな」
と、いつきが笑う。
「そのせいでどれだけ、俺たちが迷惑したと思ってるんだ」
愛想のいい顔でくくっと笑う2人。
店主が入り口の気配に気づいて、笑顔をつくった。
「いらっしゃい」
のれんをくぐる、ひとくみの子供連れ。小柄で品のいい、かっぷくのいい壮年の女性と就学前の女の子。
「おう、きたか。ひよりちゃん」
「やまちゃん、いつきくん。お久しぶり」
女性はやまちゃんの隣に座り、酎ハイを頼んで、壁に貼られた新聞を見た。
「突然、連絡がはいってびっくりしたわよ。ニュースにふうたくんが出たんでしょ?」
「そうそう」
店内には、数人の客で賑わっていて、よばれた店主は追加の注文にとりかかった。
もとから大きな店ではないがそれでも、盛況といっていいだろう。
「あいつ、ずいぶん遠いところにいっちまったよな」
「何いってんの。みんな、心はずっとそばにいるわ」
ひよりちゃんの口調も軽い。子供にはオレンジジュースを頼んで、店の隅にある絵本をもたせる。「ばあば、この新聞のおじさん、誰?」
指差した新聞に興味を持つ子供に、ひよりちゃんは笑った。
「あら、イケメンだと思わない? お祖母ちゃんの初恋の相手よ」
あれから。
ふうたは、派手に予選に敗退した。
国民体育大会成人種別 福岡大会県予選3位。
注目が集まった。
キャリアのない、まったく無名の新人が上位に食い込んだのだ。騒がれないはずがない。
栄誉ある場で、それでも、ふうたは涙を流して悔しがった。
その性格と根性に興味を持ったのが、四菱造船のスカウトたちだった。
「それから、とんとん拍子で、手が届かない存在になったんだよな」
やまちゃんがグビリとジョッキを傾ける。
「法務局の課長様が言うセリフかよ?」
いつきが景気良く笑う。
「お前こそ、営業成績1位をあっさり捨てて、居酒屋経営だろ。よくやるよ」
「いいなぁ、私なんか、もうこの歳で孫持ちよ。旦那の転勤がなかったら、この町にも戻っていないわ」
大きくため息をつく3人。
ふと、いつきがちらりとスマートフォンを見た。
時計は夜の9時を回っている。
「そろそろ、みんな。心の準備はできたか?」
気を引き締める。
「さっき、奴が駅についたんだってさ。まっすぐ、タクシーで向かっているそうだ」
3人は笑顔だ。
旧友との32年ぶりの再会。いったい何を話すのか。話は尽きないことだろう。
ちょうどその時、扉が開いて、懐かしい人影がのれんをくぐったのだった。
(了)