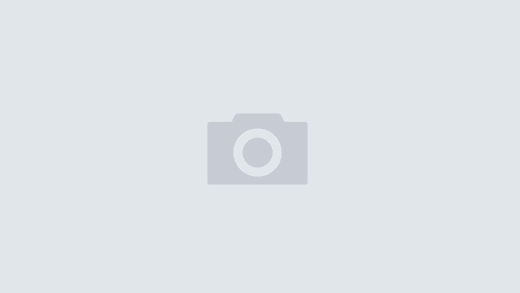西暦2053年4月21日 トーヤ=Y=オノの場合
<セクション1>
「どうして僕がこんなことに」
僕ことトーヤ・Y・オノは長崎ブリックホールの控室に立たされていた。
他でもない。アイドルたちのボディガードを、僕が務めることになってしまったのだ。
ほんの2日前にさかのぼる。
エリザベスの遺伝子上の父親、マーク・マッカートニーの前に立たされた僕は呆然としていた。
「マーク。彼らは私の若いころからの友達なの」
レディ・ヒナが僕たちを紹介してくれる。「ちなみにこちらの彼女がエリザベスで、となりの彼がトーヤくん」
「初めまして、サー=マッカートニー」
エリザベスが恭しくお辞儀し、僕もそれに続く。このへんのマナーは、幼い頃から他でもないレディ・ヒナ自身から叩き込まれたことだけど。
「ようこそ。若いおふたりさん。素敵なお名前だね。私も妻との子供が授かれるなら、君たちと同じ名前をつけるだろう」
さて、ここで真実を明かしたものか。ちらりと目をやると、日頃は楽天的なエリザベスも若干緊張気味だ。
「あら、マーク。話してなかったっけ?彼女は本物のあなたの娘よ。トーヤくんはそのパートナー」
「こいつはただのストーカーよっ!」
エリザベスが大声を上げる。
遅かった。止められなかった。
恐る恐るマークさんを見る。表情は変わらない。かなり怖い。
「ほお。つまり、君は私の娘のストーカーなのか?」
まずい。最悪の理解だ。
「い、いや・・・僕らはお互いの合意の上で一緒になったわけで」
僕らの時代では半分ロールプレイじみたありふれた単語だけど、この時代のストーカーはただの犯罪者だ。
「結局、ただの付きまといだろう?」
二の句もつげない。
「君が本当に娘を愛しているのなら、その証を見せてみろ」
出された条件が、このコンサートの警護だった。マークさんが説明するには、仕事ができる男でないと女性も守れるはずがない、というのだ。
当然ながら、僕に選択権があろうはずがなかった。
<セクション2>
「はじめまして、ユーキーでーす」
「カエデでーす」
「チアキでーす」
「リーダーのフーミンでーす。4人そろって、ラブ☆マスターズでーす」
こんな挨拶で始まる僕への仕事の依頼主は、18歳の少女たちだった。
間が痛い。
ほどほどにボイストレーニングもやっているだろうし、本職声優も訓練してきたと思われる。4人とも業界特有のやけに通る媚び声なのですぐにわかった。
そして、スタンプの仲介でそばにたった僕はかなり顔を引きつらせていた。
あれから。
すでに旧知の仲だったらしく、マークさんの申し出があるや否やスタンプたちがNAGASAKIから飛んできた。
「仕組まれていたようね。見事、スタンプの作戦にひっかかったみたい」
エリザベスが頭を抑えながら、僕の肩を叩く。「頑張れ、トーヤ。私とママは観客席から見守ってるわ」
それから、なし崩し的にスタンプが今関わっている仕事「ラブ☆マスターズ」のボディガードを引き受けることになったのだ。
空いた時間で、調べておいた。
「ラブ☆マスターズ」は、声優の卵たちが集まったグループで根強いファンのいる、ありがちなアイドルグループだ。公式ページやTwitter。インスタグラムにフェイスブック。最近のアイドル活動には、SNS展開は欠かせないらしい。
「ああ、その影響でこの規模のコンサートになったのか」
僕は舞台袖から、長崎ブリックホールの観客席を眺め、ため息をついた。
忘れられているかもしれないけど、僕はこれでもミュージシャンの卵だ。こんな大舞台は夢ですらある。振り返れば、僕が舞台に関わるのはジュニアスクールの頃 参加したウィーン声楽コンクール以来。その時、銀賞をとったことでレディ・ヒナが喜んでくれたっけ。
「ボディガードさん、何ぼーっとしてるんですか?」
リーダーのフーミンが僕に声をかけてくる。「今から私たちが歌うんですから、きちんと守っててくださいね」
「・・・はい、わかりました」
頭を下げる僕。
彼女たちをリハーサルから見ているが、そんなに歌が上手い印象はない。ここまで人気が出ているのは、事務所のプロデュースが大きいだろう。
彼女たちは幸運だ。憧れはしないが、チャンスがあるだけ羨ましいとは感じる。
コンサート開始30分前。
会場はザワザワと、緊張ムードが続いていた。
<セクション3>
その時、マーク、ヒナ、エリザベスの3人は最前列のアリーナ席でそのコンサートを見守っていた。急遽、そんな融通が効いたのは、スタンプの迅速な裏工作のおかげだ。
「ほら、始まるわよ。エリザベス」
レディ・ヒナがエリザベスの肩を叩いた。「よく逃げ出さなかったわね」
「そんなわけないでしょ。偶然とはいえパパと会えたんだし」
エリザベスがわき目でマークをみた。
「はっはっは。ひなと結婚式を迎えた1年後に、今度は大人になった娘に会えたんだ。こんな幸運があるとは思わなかった」
ひなとエリザベスが笑顔を浮かべる。足りない事情は、マークにかいつまんで話してある。
「パパは、、、トーヤの仕事ぶりを見に来たのよね?」
「そうだよ。だから、最前列を取ったんだ」
「この仕事が終わったら、彼を認めてくれるの?」
「いいや。認めるわけがないじゃないか。だって、娘のストーカーなんだぞ」
「・・・え?」
エリザベスとレディ・ヒナが顔を見合わせた。
「だって・・・」
「この仕事をやり遂げた程度で娘の許嫁に認めるとは誰も言っていない」
にやり、とマークが意地悪な顔をする。「まあ、とりあえず、度胸と根性はほめてやろう」
<セクション4>
その頃、スタンプは会場に取り付けた隠しカメラで、会場周辺を警護していた。
このコンサートへの妨害は、今の所ただのイタズラでしかなかったようだ、
コンサート開始、15分前。
開始後も気を抜けないとはいえ、無事、乗り越えることができるだろう。
そう目算していたときだった。
唐突に会場の電源が落ちた。
「停電、、、?聞いてないぞ?」
スクランブルの座標を複数ポイントにセットし転送する。
観客席は不気味な静寂に包まれた。
今から始まるのかと、わくわくの観客席には混乱はない。
観客席のひろみとかなの元にスクランブルが現れる。
「ジョージ!」「スクランブル!」
ひろみとかなの2人が駆け寄って、周囲を確認する。
「どうしたの?」
「電気系統のトラブルだ。ひろみとかな、君たちも技術者として力を貸してくれ」
<セクション5>
僕はその時、舞台袖でその混乱の中にいた。
幸い、ラブ☆マスターズのみんなに動揺はない。
「トーヤ、そっちはどうだ?」
スマホ端末に緊急通信が入って、スタンプからの連絡が届く。
「今、力強い助っ人がきたから復旧は早いはずだ。5分程度時間を稼いでくれ」
「わかりました」
とんでもないことになった。依頼主は当たり前だが、エリザベスたちは大丈夫だろうか。
混乱の中、周囲を見る。
まだ、周囲は静かだが、いつまでもごまかせるものではない。パニックが起きるかもしれない。そうなったら、怪我人どころか死者が出るかもしれない。
「ねえ。ボディガードさん、一体、何が起こったの?」
「どうやら、停電みたいですね。進行が少し遅れそうです」
僕は、アイドルたちに説明する。
4人とも少し緊張気味だ。
一体、どうしたらいい・・・?
たった今、開演時間がすぎてしまった。4人が早く歌い出さないと大騒動が起きてしまう。
修羅場の中、ひらめきがあった。
周囲を見回す。
ステージには、今にもコンサートが始まらんばかりのセッティングが施されている。
ギターにキーボード。もし、これらの楽器がもし使えたら・・・?
「4人とも、あとで僕についてくるんだ!」
僕は普段着のまま、ステージ上に飛び出した。
アコースティックギターを引っ掴んで、ステージの中央に立つ。
軽く弦を鳴らす。問題はない。思いっきり息を吸い込んだ。
腹は括っている。
できるはずだ。僕が時間を稼いでみせる。
僕は、この広い会場の隅々に届くだけの音量で、肉声だけで歌い切ろう。
ビートルズのイエスタデー。
今、これしか思い浮かばられない。
<セクション6>
「真っ暗だけど、何があったの・・・?」
そうエリザベスがつぶやいた時だった。
静かにつまびく、弾き語りの曲。
「あ、、、」
「どうしたの?エリザベス?」
レディ・ヒナがエリザベスの様子に気づいた。
「・・・あのバカ。まさか!」
その時、エリザベスたちのところにもスクランブルが現れた。
「ちょっと、スクランブル。なんでアイドルのコンサートであいつが歌ってんのよ!」
スクランブルが事情をかいつまんで話す。
「でも、、、あの曲は・・・そんなに時間稼げないわ。イントロを持たせても3分弱。長い曲じゃないんだから、、、あ」
スクランブルが何かを言いたげに、じっとエリザベスを見つめている。
「そういうことなのね。だから、昨夜、、、」
エリザベスがはっとして、スクランブルを睨みつける。
「わかったわよ!やりゃあいいんでしょ!スクランブルも来なさい!」
エリザベスも一気に立ち上がった。
<セクション7>
<セクション7>
イエスタデーは、失恋の歌だ。
昔のことを思いながら、慕う恋の歌。これほど今の僕の思いを歌った曲はない。
弦をつまびく。ギターの音を丁寧に、それでも力強く響いた。
愛が成就したと思ったその夜の悲嘆。
彼女がいない間、歌に生きた僕の1年間。
声帯を思いっきり開く。
これまで大切にしてきた思いをかける。お願いだから、持ってくれ。僕の声。
最初にざわめいていた周囲が次の瞬間、静寂に包まれたのがわかった。
気持ち、パニックに向かっていたみんなの関心を取り戻せたか。
魂と声を絞り出す。肺活量の消費量は並大抵ではない。
それでも、僕にはこれしかない。何をやってもダメな、僕が得意なことはこれだけだ。
ヘタレと言われても仕方がない。
でも、歌だけなら、、せめて歌ならば。
暗闇の中、イエスタデーを吐き出し切った時、周囲は静かになっていた。
僕の声はとどいた・・・でも。
もうこの1曲が限界だ。
絶望感。もうだめだ。コンサートが無茶苦茶になってしまう。
<セクション8>
その時、信じられない助け舟が客席から響いた。
女性の声だった。
僕ほど声量はないが、綺麗に澄んだリズミカルな声。メゾソプラノでありながら力強い女性の声。それが、ビートルズの「Let it Be」だ、と気づいた時、僕はその声の主に気がついた。
一部だけ照明が復旧して、その姿を照らし出す。
観客席からステージへ歩いてくるエリザベスの姿が浮かび上がった。
片手にワイフォンを持っている。ああ、その手があったか。一時的にスクランブルの声帯をスピーカーがわりに使ったんだ。
僕の流れがそのままつながった。周囲のパニックが再び、静まっていく。
いきなり、電源がもどった。
「さあ、ラブ☆マスターズの登場よ! みんなのコンサートを盛り上げましょう!」
エリザベスが言った瞬間、バックバンドが一気にメロディを奏で始めた。
みんなが正気に戻った。4人のアイドルたちがステージに飛び出す。
もう、僕にできることはない。
僕は満足げに、そっとステージを降りたのだった。
<セクション9>
「ありがとうございました!」
ライブが終わった時、僕とエリザベスは4人のアイドルたちに囲まれていた。
無事、何事もなかったように、コンサートは終わりを迎えることができた。
4人組とその周囲のスタッフから次々と賛辞の声が止まない。
「ねえ。マーク。これでも、トーヤくんの評価は変わらない? あの二人、お似合いだと思うんだけどな」
レディ・ヒナが笑顔を浮かべる。
「答えるのは無粋じゃないか? 決めるのは所詮、本人だ」
そう答えたマークの瞳も、微かに潤んでいる。「それに、わざわざビートルズナンバーを使うあたりに、彼らの忖度が感じられるけどな」
「そりゃあ、あなたのご先祖が歌った曲だものね」
ヒナの言葉に、マーク・マッカートニーが苦虫を潰す。
「ジョージ。つまり、そういうことだったのね?」
ひろみがスクランブルを撫でながら、そっと囁く。「昨夜、あなたがエリザベスに会いに行ったのはあのアンサーソングを教えるためでしょ?」
もし、あの場でエリザベスが「Let it Be」を歌っていなかったら、コンサートは大混乱に向かっていただろう。ひなもマークもパニックに巻き込まれて、未来が破綻してしまっていた。
「歌一曲で、HANAのリカバリー率は120%だ。完璧に、スタンプの思惑にハマったな」
ため息をつくジョージは、いつの日かスクランブルの顔に戻っていた。