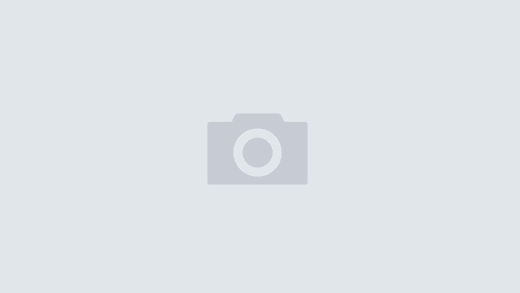かぼちゃの煮物は甘い。
特に、母が作れば、限りなく甘くなる。多分に、塩が多かったのだ。
幼少期、そんなかぼちゃの煮物を、僕は美味しい美味しいと食べ続けた。
お袋の味は、大人になると、味の基準になる。デフォルトになると、それは美味しい、おいしくないの話にならない。それが基準というものだ。
かつてのブームが今のスタンダード。きゅうりもトマトもそうだった。そういう話をどこかで聞いた。
ところが、父はなかなかカボチャに手を出さない。
義務じゃなければ、食べているところを見たことがない。
ちなみに、父の家庭菜園の収穫物は、食卓に並ぶ運命にある。
つまり、父は作っておきながら、食べないのだ。
クリショウグンやら、クリカボチャやら、頭の隅を陣取っていた記憶もある。
もっとも、僕はその恩恵を受け、父の蘊蓄を丸呑みしながら、せっせと煮物を口に運んだものだ。
父の実家は農家である。
父の育った、戦後の成長期の中で、豊かな糖質の供給源は、芋やカボチャだった。
散々、ご飯以外が食卓を彩る。
白いご飯が当たり前の現在ではとても考えられないかもしれない。
でも、白いご飯はその時代は並ばなかった。
父がカボチャ嫌いになるのはやむを得ない。
でも、畑に広がるカボチャ畑は壮大だ。
目一杯に葉が茂るから、その時期の畑の覇権は、なおさらかぼちゃが取ることになる。
育てる方は、圧巻だろう。
楽しいとすら思うかもしれない。
雌花に印をつけておき、小さく実ったら、実の表面が焼けないように、発泡スチロールの座布団を引く。
思えば、簡単に育つにもかかわらず、上品に扱われるカボチャ。
なるほど、父が夢中になるのは仕方がない。
畑のカボチャ姫のためなら、せっせと水も巻くだろう。
出来上がったカボチャの行き先は、母と僕の胃袋の中だ。
かぼちゃ料理は、いろいろ食べた記憶はあるのだが、ほとんどが煮物に化けた記憶がある。
僕はせっせと、その煮物に箸を運んだ。
しかし、そのカボチャの煮物には、ほろ甘い思い出がある。
季節は初夏だったと思う。
中学生の昼食の休憩時間。
思い思いで、楽しいひとときが繰り広げられたその光景の中、僕も例に漏れず、弁当箱を広げた。
イチゴの匂いが半径1メートルを支配した。
甘い。甘苦しい匂い。
蓋をしめる。再びあける。妙だ。
あらためて、気がついた。これは、いちごじゃない。初夏の弁当に苺がはいるはずがない。
そういえば、昨夜はカボチャの煮物だった。
当時、夕飯の残りが弁当のおかずになるのが、常だった。
それは昔の常識ではなかった。
今でこそ、冷凍食品が出回るが、当時、それは高価で。
朝の慌ただしい中、早起きするのが難しい母は、やむを得ず、前日の夕飯ののこりを弁当に入れていたのだ。
匂いだけだ。味は大丈夫、、、やっぱりだめだ。
かろうじて、箸で摘んだそのカボチャは、なおいっそう、周囲に芳しい香りを醸し出した。
弁当が腐ったのは、それが最初で最後である。
好奇心が今、うずく。
その時、腐れた煮物を一度、口に運ぶべきだった。
そうすれば、その反応だけで、クラス中の人気者になれたのではないか。
もしや、食中毒で病院に運ばれて、嫌いな英語の授業をボイコットできかもしれない。
そのひねくれ具合が、自分でも疑問には思うのだが、確かに滅多にできない経験ではある。
今日、腐れた食べ物を基本的に食べる機会はない。
貴重なチャンスだったと、のちにネタにして、僕の作文は学校の文集を飾った。
ところがである。
僕のカボチャの煮物への愛情は変わらなかった。
夕食の食卓に並ぶ、カボチャの煮物を僕は平らげ続けた。
だから、妻と二人の食卓で、カボチャの煮物はよく並ぶ。
というか、よく作る。
今夜も食べるだろう。
一度、挫折した父とは違い、根っからのカボチャ好きなのであろう。
ちなみに、最近の母は、かぼちゃを煮物にしない。
高血圧に悪いそうだ。
ふかしカボチャも悪いとは思いわないが、たまにはいいじゃないかと思わずにおれない。
ところで。最近思うこと。
一度、妻へのお弁当にかぼちゃを忍ばせ、僕の甘い中学生時代を再現したいと思うのだが、やっぱり、だめだろうか。